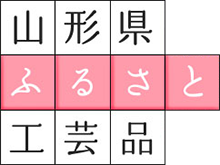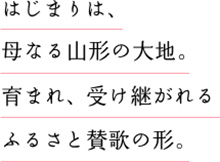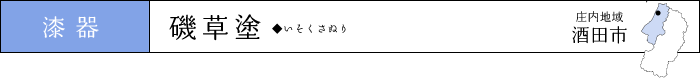

新潟から温海、鶴岡、そして酒田へ
伝承されてきた磯草塗りの技術
伝承されてきた磯草塗りの技術
新潟県で考案された磯草塗が山形にも伝えられ、温海の横堀家から鶴岡の土佐内(とさうち)家へと伝承されました。昭和26(1951)年頃から作られ始めましたが、鶴岡は竹塗りに人気があり、磯草塗はなかなか定着しなかったようです。その後、土佐内佐吉(さきち)から技術を伝えられた息子の3代目八惣八(やそはち)は酒田市の斎藤家の婿養子となり、現在は4代目八惣八氏に受け継がれています。

全工程で3~4ヶ月かかるという
緻密さと根気のいる作業の末に浮かび上がる磯草文様
緻密さと根気のいる作業の末に浮かび上がる磯草文様
縁などの消耗する部分を、米の粉で作ったのりを合わせた漆で綿布貼り付ける「布着せ」の後、輪島産の石を焼いて作った粉と生漆(きうるし)を混ぜて塗る「地の粉(じのこ)塗り」、砥の粉(とのこ)と漆を混ぜて塗る「サビ付け」をします。その後生漆に唐の土(とのつち)を混ぜた漆で「ヒボたて」を施して、磯草塗の特徴である文様の下地を作り、紅・黄・黒に緑と黄を混ぜた彩漆を塗り重ね、乾燥させてから丹念に研いで完成させます。
●茶托 ●茶櫃(ちゃびつ) ●長手盆 ●箸




![]()
斎藤八惣八
〒998-0044 酒田市中町3-2-26
電話&FAX:0234-22-1808
電話&FAX:0234-22-1808