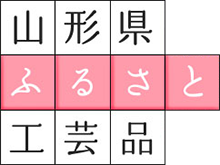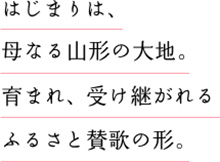米沢、長井、白鷹の各地で生まれた
高度な染めと織りの技術「置賜紬」
高度な染めと織りの技術「置賜紬」
国の伝統的工芸品に指定されている「置賜(おいたま)紬」は、米沢・長井・白鷹に伝わる紬の総称です。
それぞれの地で別々に発展した紬を、ひとつの名称に統合した経緯をふり返ります。
それぞれの地で別々に発展した紬を、ひとつの名称に統合した経緯をふり返ります。
青苧から絹織物産地へ転換した米沢藩
置賜地方の米沢・長井・白鷹近郊は、江戸時代初頭から、織物の原料となる青苧(あおそ)を栽培して越後方面に出荷する原料生産地でした。江戸後期の米沢藩第9代藩主上杉鷹山の時代になると、自給自足の織物産地を目指して、青苧を使った織物づくりを開始。肌になじむ麻織物を作るため、越後から職人を招き、縮織(ちぢれおり)の研究を行いました。凶作によって青苧織を中断した後は、領内に桑を植え、養蚕を奨励し、「絹織物生産」へと方向転換します。
米沢、長井、白鷹で生まれた高度な絣の技術
米沢藩の絹織物は、本場・京都から織物師を招いて研究開発したために飛躍的に発展。紅花や藍、紫根(しこん)などの植物染料で糸を染めて織る先染めの技術を確立します。その一方で、養蚕地だった長井・白鷹でも織りをするようになり、明治期に入ると新潟などの先進地から技術者を招き、高度な絣(かすり)技術を開発。大正期から昭和はじめにかけて、長井紬の「米琉(よねりゅう)絣」や白鷹紬の「板締小絣(いたじめこがすり)」が全国に知れ渡るようになりました。

養蚕を行い、糸を紡ぎ、染め、織りへ。鷹山公が織物政策を始めて40年後、米沢藩は全国有数の織物産地に成長しました。
時代の中で変わりゆく産地の姿
全国有数の絹織物産地に成長した置賜地域も、戦中・戦後を経て、大きく変化しました。素材は化学繊維や輸入品へ、織り技術も機械化へ。その一方で、昔ながらの草木染を手織りで行う染織家が米沢・長井・白鷹、各地に存在していました。昭和49(1974)年、国が伝統的工芸品を保護する「伝産法」を交付したことをきっかけに、そうした紬を「置賜紬」と名付け、保護、発展させようという動きが起こります。
国の伝統的工芸品「置賜紬」へ
米沢、長井、白鷹の各織物組合は、具体的にどの紬を置賜紬に指定するか検討しました。そして選ばれたのが、米沢織の「草木染」、長井紬の「緯総(よこそう)絣・経緯併用(たてよこへいよう)絣」、白鷹紬の「板締小絣」です。同時に、その技術を持つ12社が集まり、新たに置賜紬伝統織物協同組合を発足。昭和51(1976)年、それぞれの地で発展した伝統紬は「置賜紬」として、国の伝統的工芸品指定を受けるに至りました。

江戸時代、山形は日本有数の紅花産地として知られていました。多くは高級品として京へ出荷されましたが、米沢では草木染にも使われていたといいます。
置賜紬を未来へつなげていくために
「山形紅花染」プロジェクト始動
「山形紅花染」プロジェクト始動
置賜紬伝統織物協同組合の有志が近年発足した
山形紅花染織同人協議会について紹介します。
山形紅花染織同人協議会について紹介します。
途絶えていた紅花染に着目
置賜紬組合は発足以後、さまざまな取り組みを行ってきました。そのひとつが有志による「古代米琉紬」の復元です。さらに近年は、江戸時代に全国有数の産地として知られ、草木染に使われていたにも関わらず、長い間途絶えていた紅花染に着目した山形紅花染織同人協議会(以下、同人会)を発足。化学染料を多く含んだ紅花染が出回るなか、“本物にこだわった紅花染”を手がけています。
「山形紅花染」ブランド化に向けて
メンバーは、発足前から独自に紅花染を開発してきた織屋も含め、計6社。「紅花のことを理解しないと本物はできない」と、栽培から染色、織りまでを自分たちで行っています。また、紅花染の最大の難点と言われてきた色持ちの悪さも、県工業技術センター置賜試験場と実験を重ねながら克服。厳しい染色基準を設け、メンバー内の織り基準も統一し、ようやく「山形紅花染」ブランドを確立。平成19年から販売をスタートしました。

紅花は山形の県花。同人会が栽培するのは最高品種の「最上紅」です。同人会は、一緒に栽培する農家の人も含め、紅花仲間を「紅人(くれないびと)」と呼んでいます。