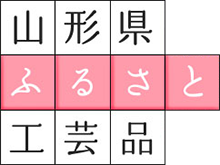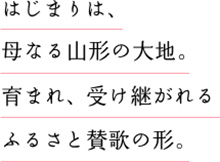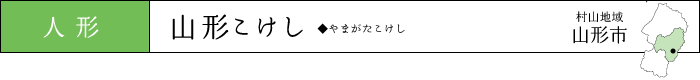

東北地方の湯治場で誕生した
木地師たちによるお土産品
木地師たちによるお土産品
こけしは、東北地方の山間地に湯治が定着した江戸時代末期、土産品として木地師が作ったことで誕生しました。現在、山形市にはふたつの系統が伝わり、「山形作並(さくなみ)系」は初代・小林倉治が万延元(1860)年、仙台藩作並の木地師に弟子入りし、その後、山形の旅籠町で木地業を開いたのが始まりで、「蔵王高湯系」は明治20(1887)年頃、福島の秋保方面から蔵王温泉に伝わったといわれています。

昔ながらの素朴な愛らしさの中に
息づく伝統と、作り手たちの個性
息づく伝統と、作り手たちの個性
伝統的な山形作並系こけしは、子どもの持ちやすさを考慮した、細い棒状の胴体が特徴です。一方、蔵王高湯系こけしは、丸みのある牡丹胴で、山形系より胴体が太くて短く、頭も大きいのが特徴です。どちらも胴には菊をはじめ、紅花やさまざまな植物が描かれます。
●こけし ●木地玩具



![]()
山形市伝統こけし工人会(小林こけし工房)
〒990-0813 山形市檜町3-11-28
電話&FAX:023-684-8866
電話&FAX:023-684-8866
山形県こけし会
〒992-0025 米沢市通町8-2-49-1
電話:0238-24-3811
電話:0238-24-3811