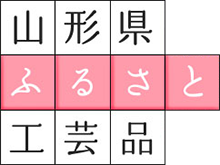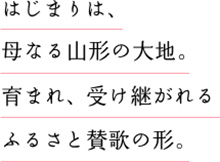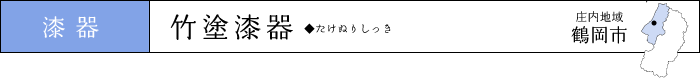

城下町鶴岡で生まれた
静かで堅牢な美しさをもつ漆器工芸
静かで堅牢な美しさをもつ漆器工芸
竹塗りは、漆を塗り重ねて竹の風情を表現する、全国でもめずらしい漆器工芸です。庄内藩の武具塗装職人だった阿部竹翁(ちくおう)が、江戸の師匠である橋本市蔵の技をもとに研究を重ね、明治期に生み出しました。華美を嫌い、ものごとの深みを美徳とする城下町鶴岡の中で、質素でありつつも静かで堅牢な美しさをもつ竹塗りは大きく発展し、弟子たちが大切に継承。現在は、鶴岡市内で塗装業を営む鈴木勇氏が受け継いでいます。

漆を盛り上げて「竹の節」を作り
色漆を何度もぼかして「枯れ竹」を表現
色漆を何度もぼかして「枯れ竹」を表現
最大の魅力は、日本独特の美意識「わび・さび」を表す枯淡な趣で、この風情は50~60日に及ぶ全36工程を経て作られます。ポイントは、「竹節」を漆で丹念に盛り上げて作ること、そして「枯れ竹」をイメージさせる色合いを何度もぼかしながら仕上げることです。またこれらの工程には、竹翁時代から変わらない「鼠の髭」や「鯨髭(くじらひげ)べら」など、今では稀少な道具が用いられています。
●茶筒 ●お盆 ●花器 ●盛器 ●箸 ●ボールペン ●すずり箱




![]()
竹塗工房 鈴木
〒997-0832 鶴岡市青柳町36-36
電話:090-7665-3710
電話:090-7665-3710